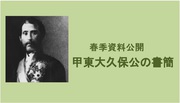
春季資料公開 甲東大久保公書簡
収蔵品明治7(1874)年~11(1878)年に大久保利通が前島密に宛てた手紙59通を全9本、巻子仕立てにしたものです。明治6年11月に内務省が新設され大久保...
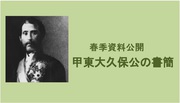
明治7(1874)年~11(1878)年に大久保利通が前島密に宛てた手紙59通を全9本、巻子仕立てにしたものです。明治6年11月に内務省が新設され大久保...

電気によって文字や絵を読み取り、それをデジタル信号に変換し、受信側に送信するのがファクシミリです。電信・電話・無線といった電気通信の歴史の中で、ファクシミリ...

明治二十九年(一八九六年)七月、それまで使用されていたガワーベル電話機に代わり、デルビル磁石式電話機が登場しました。 壁掛型でデルビル送話器を使ったところ...

電話をかけると呼び出し音の後に相手が直ぐに出て話を始められますが、その前は交換手に話をしたい相手の電話番号を伝えて繋げてもらっていました。今のようになったの...

写真は、昭和二五(一九五〇)年に青山学院大学講堂で開催された第二回全国郵便競技大会(逓信省時代から通計五回目)の様子です。機関誌『郵政』(第二巻第十二号、一...

「東海名所改正道中記」は、日本橋から京都までの五十九枚に目録を加えた六十枚で構成された一連の錦絵です。明治八(一八七五)年に三代広重によって描かれました。三...
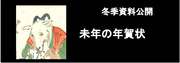
世界最初のはがきは1869年、オーストリアから発行されました。翌年、ドイツにおいて簡単な絵を私製はがきに印刷したものが現れ、数年後には絵はがきが多量に作...

有線による電気通信が、電信から電話へと進んだように、無線通信も同じような道を辿りました。 世界で初めて実用化された無線電話機がTYK式無線電話機です。TY...

写真の資料は、我が国で最初に実用化された「郵便番号自動読取区分機」(東芝製TR-4型)です。 郵便創業以来、郵便物の区分作業は、手作業によるものであったた...

東海道絵巻は、江戸時代初期から中期の東海道を描いた絵巻物です。「江戸御本丸から「京二条御城」までが描かれており、街道沿いの名所旧跡はもちろん、河川や山などの...